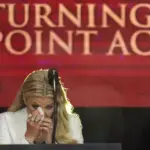若者の間で「ガラケー」復活 「ドーパミン・ダイエット」と専門家

ニューオーリンズで複数のアプリを表示するiPhone。(AP Photo/Jenny Kane, File)
By Emma Ayers – The Washington Times – Friday, April 18, 2025
静寂と集中、少しでも自分の人生を取り戻そうと、スマートフォンを捨てて「ガラケー」に移行する若者が増えていることが、最近の研究で明らかになった。
専門誌「パートナーズ・ユニバーサル・イノベーティブ・リサーチ・パブリケーション」の最近の研究によると、2021年から2024年にかけて、18歳から24歳への「携帯電話」の売り上げは148%急増し、スマートフォンの利用は12%減少した。
この現象を専門家は「幸せホルモン」の一つとして知られるドーパミンにちなんで「ドーパミン・ダイエット」と呼んでいる。
ニューヨーク工科大学心理学准教授のメリッサ・ディマルティーノ氏は、ヤフー・ライフとのインタビューで、「スマートフォンは、薬物やアルコールと同じ化学反応を脳内で起こす。気分を良くするためにスマホを見ることは、中毒性のサイクルとなり、最終的に人々を憂鬱で孤独な気分にさせる」と述べている。
デジタルメディアの専門家らは、携帯電話の復活はノスタルジーから始まったが、TikTok(ティックトック)で火がついたと言う。ハッシュタグ#bringbackflipphonesによって、Z世代の間でこのレトロなコミュニケーションツールが再びトレンドになっている。
英紙ガーディアンによると、有名な折り畳み携帯電話「ノキア3310」のメーカーであるHMDは、この携帯電話が2017年に再発売されて以来、2023年時点で売り上げが倍増していることを明らかにした。「ミニマリストフォン」を売り文句とするPunktも売り上げが上昇した。
決済調査会社PYMNTSインテリジェンスの2024年のリポートによると、あらゆる年齢層の中でZ世代だけがデジタル機器の保有が減少している。同社は、全米平均が5.0台から5.1台に微増した一方で、Z世代が所有する(インターネットに接続可能な)コネクテッドデバイスの平均台数は2019年と2020年の5.3台から2023年には5.0台に減少したと報告している。
ロンドンでサーヤ・センとして活動しているZ世代の音楽プロデューサー、ラナ・アリさんはガーディアン紙に「私はいつでも、誰にでもつながれることがいいとは思っていない。メッセージを送ったのに、すぐに返事が来ないと考えるのは、どこか間違っていると思っている」と述べている。
デジタル機器の専門家によれば、若者たちは何かをつかんでいるかもしれない。米科学アカデミーの専門誌「PNAS
Nexus」が2025年に発表した実験結果によると、モバイル機器でのインターネット接続を禁止し、通話やメールは許可すると、精神衛生、注意力、全体的な幸福感が改善した。
2週間のデジタル機器禁止の後、参加者の91%に幸福感の改善が見られた。研究者によれば、オフラインの時間は人との交流、運動、外出などに費やされたという。
ニューヨークの「ラッダイト・クラブ」の10代の若者たちは、毎週このような時間を過ごしている。ブルックリンのプロスペクトパークで電話を持たず、話したり、絵を描いたり、本を読んだりしている。
ブルックリン工業高校に通うジェイムソン・バトラーさんはCBSニュースに「1日が8時間長くなった」と述べた。このクラブに入る前は、新型コロナの感染拡大の中で画面を見ている時間が急増していたという。
エドワード・R・マロー高校の元教師で、現在はこのクラブについてのドキュメンタリーを共同監督しているアマンダ・ハンナマクラー氏はCBSに「今、目の当たりにしているのは、技術の利用ではなく乱用だ」と語った。
Z世代の5分の1以上が「スマートフォンが発明されなければよかった」と答えていることが、社会心理学者ジョナサン・ハイドと共同で実施した2024年ハリス世論調査で報告された。調査は18歳から27歳のZ世代成人1006人を対象に実施され、その半数近くがティックトック(47%)、スナップチャット(43%)、X(50%)がなければよかったと答えている。
アイオワ州に住む19歳のケイレブさんにとって、スマホをやめることはつながりを断つことだったが、彼にとってはそれだけの価値があった。
ケイレブさんはヤフー・ライフに「スマートフォンを段ボール箱に入れ、ガムテープで3重に包み、1週間別れを告げた」と語った。
今ではそれに慣れ、折り畳み携帯とノートとMP3プレーヤーを持ち歩いている。
「自分の経験を日記に書く方が、自分らしく感じ、充実感が得られるからだ」
ニューヨークを拠点とするアーティストで、Z世代のインフルエンサー、オーガスト・ラムさんは、スマホなしの生活への道をゆっくりと進んだ。
20代の画家ラムさんはナショナル・パブリック・ラジオ(NPR)に「電車の中でオーディオブックを聴きたいとか、道案内が必要だとか、どうしてもその日にスマートフォンが必要だと思うようなことがあると、またスマートフォンに吸い込まれてしまう」と語った。
彼女は2022年以来スマホを持っておらず、イラスト入りのガイドを作成して他の人にもスマホを持たないことを勧めている。次はノートパソコンを処分するつもりだという。
「どうしたらいいか分からないって感じることはよくあるはず。でも、いざその道が閉ざされてしまうと、どうにかしてやり方を見つけるものだ」
精神衛生の専門家によれば、電源を切りたくなる衝動は神経科学に基づくものだという。そして、サイレントモードは必ずしも助けにならない。
カーネギーメロン大学のアリ・ライトマン教授(デジタルメディア)は、ヤフー・ニュースにこう語った。「一度電話を開けると、パンドラの箱を開けたようなものだ。一種の連鎖的なアクションが、あなたの時間をすべて奪ってしまう」
これらの若いデジタルミニマリストは、ガラケーはこの連鎖を断つのに役立つと主張している。
社会学者でデジタルミニマリズム団体「オーセンティック・ソーシャル」の創設者、ケイトリン・ベッグ氏は、「古いシステムは、アルゴリズムに支配されることはなく、人が一度に1つの活動に集中することを可能にする」と言う。
それでも、スマホを念頭に置いて作られたデジタル文化の中で、スイッチを切り替えるのは必ずしも容易ではない。アラバマ州に住む24歳のある女性は、ヤフー・ライフの取材に対し、2023年に4Gと全地球測位システム(GPS)を備えた携帯電話を見つけるのに苦労したが、諦めずに探し続けていると語った。
「周りの世界ともっとつながっていると感じたいし、自分がいいと思うものを通じてつながっていたい。ただぼんやりと聞いたり見たりして、二度と戻らない何時間もの時間を無駄にするのはもう嫌だから」