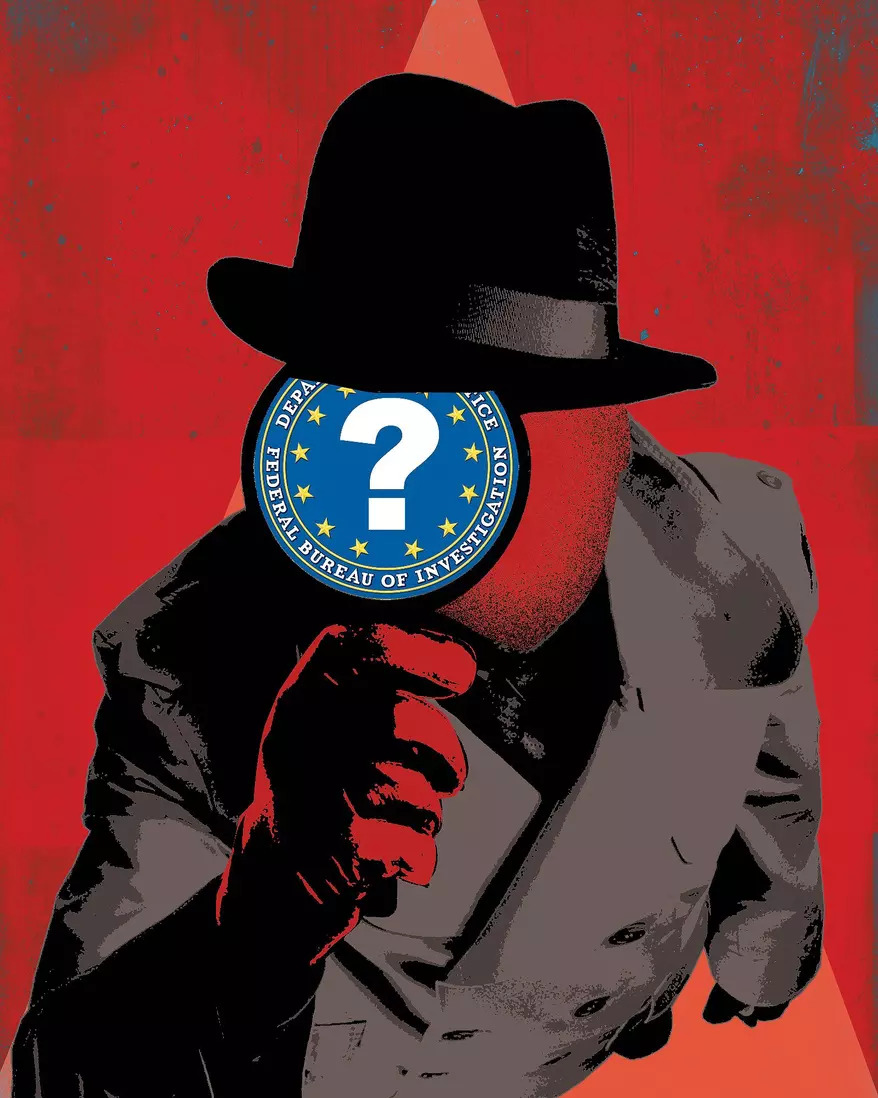ニュース

中国版「トップガン」、国民に反米感情植え付け
(2023年5月19日)
バイデン政権が中国との紛争の回避を模索する一方で、中国共産党は、将来の米国との戦争に備えるよう国民に訴えかけるメッセージの発信を強化している。
人民解放軍(PLA)空軍を描いた中国の新作映画「長空之王」もその一つ。先月下旬に公開され、米国の大ヒット映画「トップガン・マーヴェリック」(2022年)に対抗することを狙ったものとみられている。 →続き
人民解放軍(PLA)空軍を描いた中国の新作映画「長空之王」もその一つ。先月下旬に公開され、米国の大ヒット映画「トップガン・マーヴェリック」(2022年)に対抗することを狙ったものとみられている。 →続き
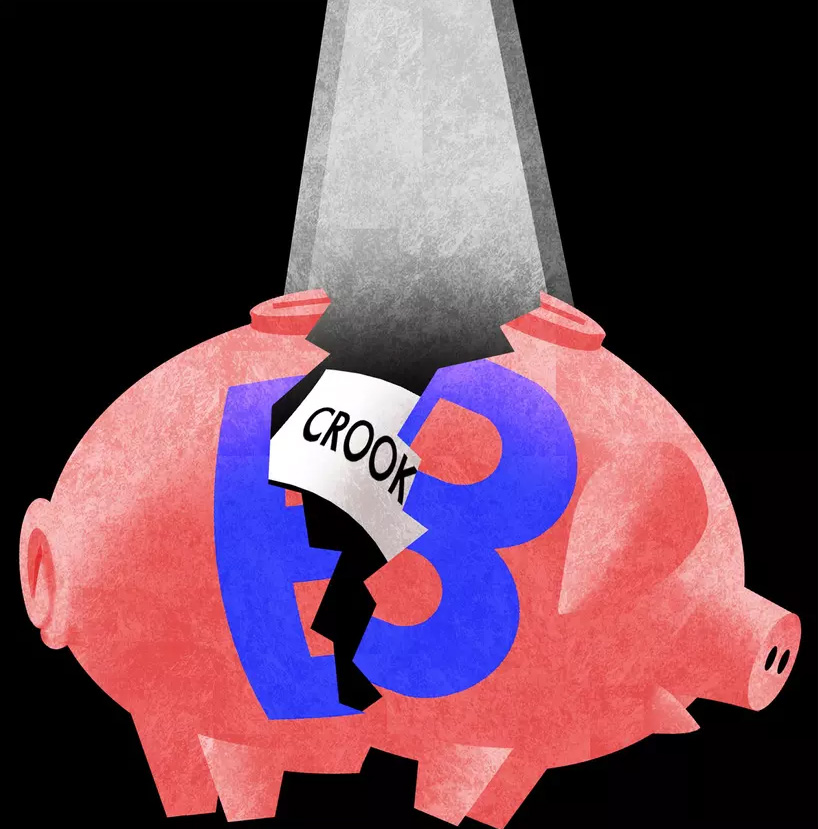
「ホワイトハウスの審判の日」バイデン家汚職疑惑が過熱
(2023年5月17日)
影響力行使の疑惑は、バイデン大統領の「バイス(副)」大統領という古い肩書に新たな意味を与えている。司法省は、バイデン一家の金銭的不正の疑惑を何年もかけて調査してきたが、その努力はほとんど報われなかった。
だが、議会につきが回ってきたのかもしれない。バイデン氏に2期目を与える前に、バイデン氏とその家族が、汚職に手を染め、外国のために便宜を図っていないかどうか、国民は十分に知るべきだ。 →続き
だが、議会につきが回ってきたのかもしれない。バイデン氏に2期目を与える前に、バイデン氏とその家族が、汚職に手を染め、外国のために便宜を図っていないかどうか、国民は十分に知るべきだ。 →続き

性転換求める子供の行方を親に知らせない新法成立-ワシントン州
(2023年5月15日)
ワシントン州では、子供が中絶や性転換のための薬や手術のために家出した場合、保護者に直ちに通知されなくなる。
ジェイ・インスリー州知事が9日に署名したこの法律は、家出した子供が「保護された医療サービス」を求めたり、受けたりする場合、青少年保護施設や子供を受け入れている家庭は行方不明の子供の所在を親に知らせないことを認めている。 →続き
ジェイ・インスリー州知事が9日に署名したこの法律は、家出した子供が「保護された医療サービス」を求めたり、受けたりする場合、青少年保護施設や子供を受け入れている家庭は行方不明の子供の所在を親に知らせないことを認めている。 →続き

大学では保守派を無視した卒業式が行われる
(2023年5月14日)
大学キャンパスで保守的な講演者はすでに少ないが、今春の大学卒業式では、左派の教育者、芸能人、政治家などが多い一方、右派は皆無に等しいため、さらに異例なことになるかもしれない。
尊敬されている学者であれ、最高裁判事であれ、あるいは元大統領であれ、ほとんどの米国の大学からのメッセージは明確だ。「保守派はお断りです」 →続き
尊敬されている学者であれ、最高裁判事であれ、あるいは元大統領であれ、ほとんどの米国の大学からのメッセージは明確だ。「保守派はお断りです」 →続き

台湾駐米代表、中国の脅威に非対称兵器で対抗
(2023年5月13日)
台湾の民主主義は、中国からの軍事的脅威と「グレーゾーン」情報戦の両方に直面しており、自衛のために非対称兵器を採用する―台湾の駐米代表はインタビューでこう語った。
台湾の蕭美琴駐米代表(大使に相当)は、米国の投資家ウォーレン・バフェット氏が、中国の脅威によって、台湾はビジネスを行う上でますます危険な場所となりつつあると主張したことに異議を唱えた。 →続き
台湾の蕭美琴駐米代表(大使に相当)は、米国の投資家ウォーレン・バフェット氏が、中国の脅威によって、台湾はビジネスを行う上でますます危険な場所となりつつあると主張したことに異議を唱えた。 →続き

ウクライナ・ロシア:ハイテクを駆使した第一次大戦?
(2023年5月12日)
【フロリダ州タンパ】それは主要大国の間で展開された初めてのハイテク衝突であり、21世紀に進化する戦闘を間近に見極める紛争になるだろうと言い交わされた。しかしロシアとウクライナの戦争は、ドローンやアイフォンを駆使した第一次世界大戦、とでも言えるような、戦術や戦略では大方の予想よりもはるかに、伝統的なアプローチに多くの共通性がある、一部のアナリストはそう指摘している。
確かにこの戦争では現代の技術、例えば無人航空機、高度な通信システム、次世代型ミサイル防衛システム、ソーシャルメディアなどが重要な役割を果たしている。しかし15ヶ月目に入った戦場の核心部分では大砲、地上での機動作戦、戦車戦や、一世紀以上も前の第一次世界大戦を思わせる深く掘った防御用の→続き
確かにこの戦争では現代の技術、例えば無人航空機、高度な通信システム、次世代型ミサイル防衛システム、ソーシャルメディアなどが重要な役割を果たしている。しかし15ヶ月目に入った戦場の核心部分では大砲、地上での機動作戦、戦車戦や、一世紀以上も前の第一次世界大戦を思わせる深く掘った防御用の→続き

差別撤廃政策の難題に名判決はあるのか
(2023年5月12日)
最高裁判所は判事の任期を終えるまで、今後二か月足らずに、人種、信仰の自由、投票権、ソーシャルメディアの在り方、同性愛者の権利など、今の合衆国が抱える難題を判断しなければならない。
同じく二つの事案で、バイデン行政の行方を決定する判断に迫られている。その一つは学生ローンの返済免除方針について、もう一つは不法移民を寛大に処遇する方針についてのものだ。 →続き
同じく二つの事案で、バイデン行政の行方を決定する判断に迫られている。その一つは学生ローンの返済免除方針について、もう一つは不法移民を寛大に処遇する方針についてのものだ。 →続き