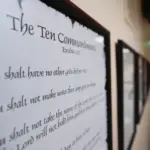中絶については中国、北朝鮮と共同歩調を取る米国

2022年1月25日(火)、カンザンス・フォー・ライフの行進中、支持者によって持たれる中絶反対の看板(カンザンス・フォー・ライフ)。(Evert Nelson/The Topeka Capital-Journal via AP)
By Sean Salai – The Washington Times – Monday, January 31, 2022
米国とその他の国々を比較した調査によると、妊娠の全期間で無条件の中絶を認めている国は、米国、中国、北朝鮮など6カ国だけであることが分かった。
キリスト教福音派団体「家庭調査協議会」が先週発表した報告書によれば、その他の3カ国はカナダ、ベトナム、韓国だという。
全体では69カ国が選択的中絶を認めており、そのうち58カ国が妊娠14週目以降、つまり妊娠第1期直後からの中絶を制限していることが、この報告書で明らかになった。
「米国の中絶に関する法律は、全ての人の尊厳を守る国々ではなく、北朝鮮や中国のような人権侵害国の法律に近い」。報告書の主執筆者で、同団体の「人間の尊厳センター」のディレクターを務めるマリー・ゾック氏はこう語った。「米国民は自国民を強制収容所に入れるような国々ではなく、全ての人に生きる権利があると信じる国々と一致するような法律に変える取り組みをしなければならない」
報告書によると、調査した約200カ国のうち99カ国が受胎の瞬間から中絶を禁止、またはレイプや近親相姦、母体の生命を守る場合のみ中絶を認めている。
「世界の中絶法を調査した結果、一つはっきりしたことがある。それは、大多数の国々が子宮内の胎児の生命を守る法律を持っているということだ」と、報告書は指摘している。
調査によると、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、スイスなどほとんどの欧州諸国に加え、ロシア、オーストラリアも、妊娠14週以降の中絶を制限していることが分かった。
ナイジェリア、ケニア、モロッコなど多くのアフリカ諸国、ペルー、パラグアイ、ベネズエラなどの南米諸国は、母親の生命が危険にさらされている場合を除いて中絶を違法としており、26カ国が例外なく選択的中絶を禁止している。
一部の国では、胎児の異常や精神障害、社会経済的な制約を例外として認めている。
家庭調査協議会で生命と人間の尊厳に関する連邦問題担当部長を務めるコナー・セメルズバーガー氏は、アナリストのジョイ・ザバリック氏と共にこの報告書を執筆した。セメルズバーガー氏は、この調査結果について、無制限の中絶が広く受け入れられ、実行されているという仮定を覆すものであると述べている。
「中絶産業は、米国の過激な中絶法が世界の標準であるという認識を与えているかもしれないが、それは真実から最も遠いものだ」と、セメルズバーガー氏は語った。
米連邦最高裁は、ミシシッピ州が15週以降の中絶を禁止したことを審理しており、中絶を全米で合法化した1973年の歴史的な「ロー対ウェイド判決」を覆す可能性がある。昨年12月の「ドブズ対ジャクソン女性保健機関」裁判の口頭弁論で、ジョン・ロバーツ最高裁長官は、無条件の中絶に関して米国は国際的な例外国だと指摘した。
一方、ギャラップ、マリスト、ピュー・リサーチ・センターといった世論調査機関が最近行った調査では、米国民の過半数が無条件ではないとしても、何らかの形の中絶を支持していることが分かっている。
しかし、家庭調査協議会の報告書は、昨年6月に公表されたAP通信・シカゴ大学全米世論調査センター(NORC)の調査結果を引用し、米国民の65%が妊娠第2期の中絶は「ほぼ常に」違法であるべきだと答え、第3期では80%がそう答えたとしている。